早稲田大学ビジネススクール教授 平野正雄氏(3/3ページ)

投資家・コンサルタントの立場から見た理想のCFO像など、様々な見解をお話し頂く専門特集。
マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社長、カーライル・ジャパン共同代表を経て、現在、早稲田大学ビジネススクール教授を務める平野正雄氏に、これまでの経験の中で感じる率直な思いを伺った。
※インタビュアー/株式会社Widge 代表取締役 柳橋貴之

平野さんから見られた「CFO」に関するお考えもお伺いできますか。
これまでコンサルタントとして、投資家として、多くの日本企業の経営を支援し、関わらせていただきました。現場のメンバーも経営に関わる方々も極めて優秀で、誠実な方々も多いですし、少しでも事業を良くしていこう、会社を良くしていこうという思いも強いと感じています。仕事柄、欧米の経営者、欧米の企業も知っていますが、決して劣るものはないですし、むしろ日本の企業の方が自社に対する思い、コミットが強いという感覚もあります。これは日本の企業の美質であり、そういった価値観は非常に優れたものだと思います。
ただ、その中で欠落しているもの、不十分なものがあるとすれば、「経営の規律」であり、「ドライブ」に関してですかね。
「規律」、「ドライブ」ですか。
先程申し上げた美質が、逆に既存の事業を守ることや、雇用を維持することに過剰な意識が向かってしまい、今、すべき決断が先送りされてしまったり、踏み込んだ改革を躊躇することに繋がってしまうのです。
前に進めていく力であったり、「必要な改革は躊躇なく進めていく」という決断力が十分ではないため、結果、中長期的には競争力が蝕まれていくことがあります。
なるほど。
そうさせないのが「規律」なのです。その規律はどこからくるのか。もちろん理念、思いも大事なのですが、非常にソフトな要素なので、測定がとても難しいのです。達成できているかどうかも、評価が難しいものなのです。
一方、数字は極めて明確です。一番重要なことは会社の価値ですが、企業価値、正確に定義すると株主価値は、どれだけの新たな経済的価値を生み出せるか、明確に測定することも比較することも、目標設定もできます。
そうですね。
当然、経済的価値だけのために企業が存在しているわけではありません。ただ、一つ明確な指標で目指すべきものを定めない限り、企業には多くのステークホルダーが存在するので、数多くの自社で定めた業績指標やKPIなどに加えて、そこに様々な配慮や忖度、政治的要素などが絡んでくると、意思決定そのものに鋭角性、明確性を欠いていくことになるわけです。

仰る通りですね。
結果的に何を高める必要があるのかを明確にしていく。きちんと見えるものにしていくことで、最終的には企業価値が重要になります。上場会社であれば、議論の余地はないわけです。企業価値あるいは株主価値を明確に見ていくのが、つまり「ファイナンスの力」「ファイナンシャル分析の力」になっていくわけですよね。CFOはそこを担う人なのです。
まさにそれがCFOだと。
企業の状況、事業の実態を、数値化の指標、財務的な指標を通して明らかにしていく。それを経営者、経営チームに伝え、意思決定を促していくということが非常に重要ですし、経営判断の材料、中核的な材料にするということが非常に重要なわけです。それが規律です。そういうことができるのがCFOです。
「規律」の材料を明確に揃えていくのがCFOということですね。CFOが持つべき資質とは、何かございますか。
もちろん財務的な知識や分析能力は必須ですよね。ただ、これが全て個人の中にあるというよりも、CFOのチームに備わっていればということです。そして、経営者や事業部門と対話をして、ある時は説得をしていくということも必要ですよね。事業や経営を評価し、理解をする力、あるいは財務や経理の言葉というものを事業や経営の言葉に転換できる力、翻訳する力を持っていないといけません。これはCFOとして非常にクリティカルな能力だと思います。
確かにこの辺りはとても重要ですね。
そういう能力を持ったCFOが経営チームにいれば、最終的なボトムラインである価値向上より、様々な業績指標、施策の優先順位、時間軸の決定などということに関して明確な基準を提供していくことができ、経営者がそれを認識することによって意思決定が進められていく。こういう流れができると、非常に強い経営になると思います。
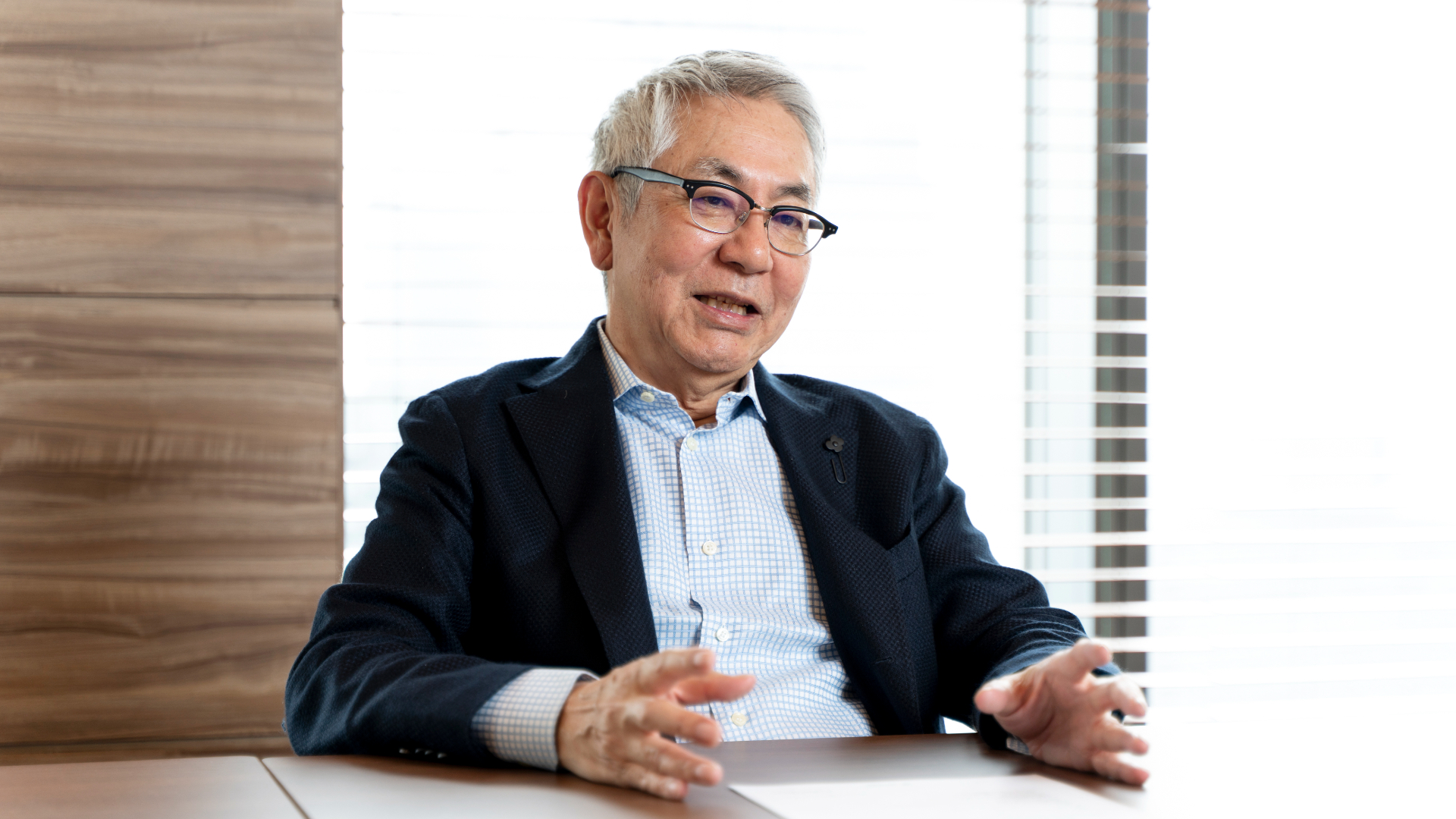
一つ、PEファンドとの関係で申し上げると、PEファンドが企業に持ち込むものは何かというと、資金提供や経営のアドバイス、人材の紹介などはもちろんなのですが、経営に「時間感覚」を持ち込むんです。
「時間感覚」ですか。
ファンドは一定期間を経たらEXITする必要があるので、時間感覚が非常に発達しています。通常4年~5年くらいのスパンなので、仮に5年だとすると、5年の間に改革をやりきらなければいけません。そのプランを持って投資するので、経営者と合意し、しっかりと5年間でやりきるということです。ですから、明確な時間軸が定まります。
大概の日本企業の方たちは、やらなければならないことは分かっています。ただ、分かっているものの、それを今すぐにやらない。これが問題なのです。
時間に対するコスト感覚が希薄しているということなのですね。
はい。まさにそうです。それを持ち込むのがファンドの力なのです。では、ファンドに頼らなければいけないのかというとそういう事はありません。ただ、それをやらないと今度はアクティビストが来るわけです。
確かにそうですね。
アクティビストは、やらなければいけない改革のことをただ言っているだけなのです。おそらくそれは、ボードや経営チームではずっと議論されていることなんです。例えば、「いつこの事業から撤退するのか」、「いつこのコストを下げるのか」。ただ、「まだやっていない」「まだやれていない」ということなのです。ですから、アクティビストに入り込まれて、マーケットも値がつかないとなると、経営の評価が下がって、バリュエーションが下がる。株価が下がると、またそこにアクティビストが目をつける。
そういう悪循環になるわけですね。
何が原因かというと、先ほど申し上げた「規律」と「時間感覚」が不足しているということなのです。この「時間感覚」を経営に持ち込むのも、CFOの重要な役割になってきます。

「時間感覚」というキーワードは重要ですね。
財務の方は当然鋭敏なはずです。そもそも金利は時間コストみたいなものですよね。時間は極めて重要な限られた資源でもあるし、コストでもあるという認識があります。そういう概念を経営に持ち込むことが非常に重要なのです。
とても納得感があります。
日本の企業には、しっかりとした戦略があり、良い商品があり、販路もあり、優秀な社員もいます。何が一番欠けているかというと、時間軸を明確に持ち、的確なタイミングで、強い意思決定をして前に進めていくこと。ボトムラインとして企業価値を高めていくこと。外から見て分かる目標につなげていくということです。繰り返しになりますが、CFOは非常にクリティカルだということです。

CFOとして活躍されている方々へのアドバイスをいただけたら嬉しいです。
CFOは財務の専門家ということだけではありません。経営のメンバーです。常に経営者感覚を磨いていくことはすごく重要なことです。これが本当に大事だということを強調しておきたいと思います。
単なる財務の専門家ではないということですね。
求められる知識、能力、視野が全く違うということです。CFOをされている方、目指される方は、そこを意識することがとても大事ですね。これは私の感覚ですが、米国のCEOのバックグラウンドのうち、CFO出身の方はかなりの割合を占めていると思います。
日本の企業でも、少しずつですが、CFO出身のCEOが誕生してきました。ただ、まだまだ限られているのが現状です。
名CFOと言われる方はたくさんいらっしゃいますよね。ただ、なかなかCEOには届いていないこともあります。その会社の決め方によるところもあるとは思いますが。
ですから、ある会社のCFOが他の会社に行ったらどうか、架空の議論ですが、全然違うことになると思います。何が一番潜在価値が高いのか、価値を生むところに集中すること、どうやって企業価値を生むかということで、合理的な意思決定をしていくということです。
まさにそうですね。
「財務屋だろ、経営は無理じゃないか」みたいなのはとんでもないことであって、むしろ、経営者がその視点を持っていないのは極めて危険だということです。経営者はそういうCFOセンスを持っていないとダメなんですよね。そういう意味で言うと、極めて一衣帯水という関係なのかもしれません。
ありがとうございます。これは私も様々な場面で伝え続けている点でもあり、腑に落ちます。他に、もしお伝えしておきたいということがあればお願いします。
一番大きい役割は「経営の規律」、「時間感覚」と申し上げましたが、このご時世であと二つあるとすれば、「リスクマネジメント」と「テクノロジー」でしょうか。
リスクマネジメント、危機対応力。安全保障で荒れることがあっても、そういった時に耐えられるような体制を作り上げるということが大事です。もう一つのテクノロジーについては、AI、かっこよく言うとデータワークですけども、財務諸表を高度な分析を通して、経営や事業へのインプリケーションを出していくことが今後ますます重要になってくると思います。
大変勉強になりました。本日は貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。

1980年、日揮株式会社入社。プラントエンジニアリングの業務に従事。
1987年から20年間、マッキンゼー&カンパニーにて経営コンサルティングに従事。主に日本の製造、消費財、通信分野の企業各社に対して企業成長戦略、海外展開、M&A、および組織改革などのアドバイスを提供。この間、1998年から2006年までマッキンゼー日本支社長として、日本における業容拡大を推進。
2007年、プライベート・エクイティ大手のカーライル・グループ日本の共同代表に就任。産業材、製薬、外食、ソフトウェア開発などの多分野の日本企業のMBOを支援。各社の企業価値向上を実現すると共に、投資の出口戦略として成功裡に株式上場あるいは大手上場企業への株式譲渡などを実行。
2012年より早稲田大学ビジネススクール教授。並行して、複数の企業の社外役員や顧問を務めると共に、政府の各種委員会の座長および委員を歴任。




